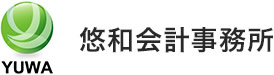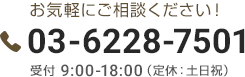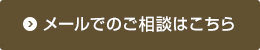登録免許税及び不動産取得税に関する軽減措置が、2023年税制改正により延長されています。
一般の個人・法人からファンドまで広く恩恵を受けることができます。
登録免許税、不動産取得税に係る軽減措置が2年ないし3年延長
【登録免許税】
| 所有権移転 (通常税率 2.0%) |
所有権保存 (通常税率 0.4%) |
|
| 土地の売買 | 1.5% (2026年3月末まで) |
0.4% |
| 個人の住宅用家屋 (50㎡以上の新築または一定の中古) |
0.3% (2024年3月末まで) |
0.15% (2024年3月末まで) |
| 特定目的会社、 投資信託、投資法人 |
1.3% (2025年3月末まで) |
0.4% |
| 不動産特定共同事業法 | 1.3% (2025年3月末まで) |
0.3% (2025年3月末まで) |
| 経営力向上計画の認定を受けた 土地・建物の取得 |
事業譲受:1.6% 合 併:0.2% 会社分割:0.4% (2024年3月末まで) |
– |
【不動産取得税】
| 土地(宅地) | 住宅用家屋 | 住宅以外の家屋 | |
| 【税率】 | 3.0% (2024年3月末まで) |
3.0% (2024年3月末まで) |
4.0% |
| 【不動産取得税の計算( = 課税標準×上記税率)】 | |||
| 一般 | 不動産価格×1/2×税率 (2024年3月末まで) |
不動産価格×税率 (※) |
不動産価格×税率 |
| 特定目的会社、 投資信託、投資法人 |
不動産価格×2/5×税率 (2025年3月末まで) |
||
| 不動産特定共同事業法 | 不動産価格×1/2×税率 (2025年3月末まで) |
||
| 経営力向上計画の 認定を受けた取得 (事業譲受のみ) |
不動産価格×5/6×税率 (2024年3月末まで) |
||
登録免許税については、今回の税制改正により以下の軽減措置が延長されました。
● 土地売買の所有権移転登記: 2.0% →1.5%
● 特定目的会社、投資信託、投資法人等が取得する一定の不動産に係る所有権移転登記: 2.0% →1.3%
● 不動産特定共同事業事業法に基づき取得する一定の不動産に係る登記
所有権移転登記: 2.0%→1.3%
所有権保存登記: 0.4%→0.3%
また、不動産取得税に係る軽減措置についても、以下の延長が行われました。
● 特定目的会社、投資信託、投資法人等: 5分の2に軽減(5分の3を控除)
● 不動産特定共同事業者: 2分の1に軽減
適用の可否や軽減効果を検討するにあたり、新築・中古、用途、面積等の要件を細かく確認する必要があります。
コンマ数%の違いでも収支に大きな影響を及ぼす不動産流通課税。 軽減措置の延長は一般国民や事業者にとってありがたい支援となります。