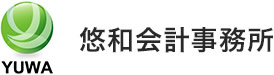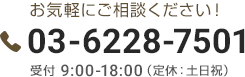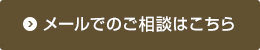投資家の行き過ぎた減価償却を規制する流れが続いています。
2023年税制改正では、一定のコインランドリーやマイニングマシンが投資優遇税制の対象から除外されました。
コインランドリー節税に一定の歯止め
購入した資産が中小企業経営強化税制の適用対象であれば、即時(100%)償却が認められます。
一部の富裕層や投資家はこれを利用し、所得が見込まれればコインランドリーやマイニングマシンを購入して、その全額を損金に計上する節税(税金の繰延)を行っていました。
今回の税制改正では、これに一定の歯止めが掛けられました。
| 中小企業経営強化税制 | 中小企業投資促進税制 | |
| 減価償却 | 100% | 通常の償却+30% |
| 税額控除 | 10% (資本金3,000万円超の法人は7%) |
7% (資本金3,000万円超の法人は不可) |
| 2023年税制改正 により優遇除外 |
コインランドリー業/ 暗号資産マイニング業 |
コインランドリー業 |
| 優遇除外 されるケース |
主要な事業ではなく、管理の概ね全部を他者に委託するもの | 同左 |
コインランドリー業や暗号資産マイニング業が「主要な事業」に該当すれば、規制はされません。
例えば、以下のケースであれば、これまで通り優遇税制による減価償却や税額控除が可能です。
● 自社の役員や従業員の多くが携わっている事業
● 新規事業として自社の土地や建物を活用して行う事業
● ある主要な事業の利用者に向けたサービス提供のために行う事業
また、「主要な事業」でなくても、事業の全体管理や業務の全部または一部を自社の役員や従業員が実施している場合は、規制対象からは外れます。
すなわち、事業として設備投資するのではなく資金のみ拠出する投資家が、優遇税制の対象から除外されることになります。
10万円未満の少額資産、個人の海外不動産に続き、富裕層が好む減価償却の抜け穴が塞がれていきます。
関連コラム:
(2020/11/30) 2020年ファンド・投資税制④ ~海外不動産の節税防止~
(2022/2/28) 2022年ファンド・投資税制① ~10万円未満の即時償却目的の投資が規制~